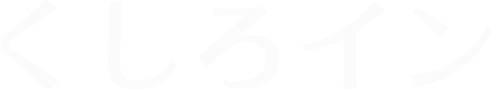北海道 釧路の地酒 『福司』 若僧蔵人の醸し屋日記 - 記事一覧
http://fukutsukasa.blog64.fc2.com/
| 発行日時 | 見出し |
|---|---|
| 2026.02.17 |
なぬ!?KAS FES 〜酒粕フェス〜


東京でお取引のあるSAKE Streetさんが、
酒粕の美味しさや使い方を伝えるイベント 「KAS FES 〜酒粕フェス〜」を開催します。 今年、どうですか?とお声がけをいただき、 五色彩雲として参加させていただくことになりました。 (酒粕を提供するだけですが……) 正直、東京はすごい。 酒粕でフェスができるなんて。 酒粕をもっと身近に!バージョンアップした KAS FES 2026で酒粕をおつまみに日本酒を飲もう そして今回のKAS FES、 当日提供する酒粕とあわせて日本酒の試飲もできるとのこと。 それならばと、 五色彩雲から特別な酒粕を出させていただくことにしました。 札幌国税局の新酒鑑評会・純米の部に出品予定の 五色彩雲「Jiri」の原酒、その酒粕です。 おそらく今回のKAS FESでしか手に入りません。 弊社としては、かなりの貴重品。 現在、麹のストッカーで大事に保管しております。 独特の造りをしているJiriの酒粕を、 “酒粕のプロ”ともいえるさけかす子さんが どのように料理してくれるのか、私も楽しみにしています。 酒粕の活用は、どの蔵にとっても課題です。 酒を造れば、必ず生まれるもの。 多い蔵では、酒と同量ほどの粕が出ます。 福司ではできるだけ出過ぎないように意識していますが、 それでも必ず生まれる。 正直、「粕」という名前もあまり良くないなと思っています。 先人たちは上手に活用してきましたが、 現代では独特の風味から敬遠されることも少なくありません。 でも栄養価は高く、機能性もある。 まだまだ可能性がある素材だと思っています。 酒と同じように、 酒粕にもきちんと価値がつけば、 酒蔵はもっと前向きに酒造りができる。 結局のところ、 一番の解決策は「食べてもらうこと」。 東京での挑戦が、 酒粕の可能性を少しでも広げるきっかけになれば嬉しいです。 食品加工や開発のご相談、いつでもお待ちしております(笑)。 酒粕のできるようす・・・・できて剥がされていく様子を こちらの動画でもぜひご覧ください 」」」」」」」」」」」」」 SNS情報 」」」」」」」」」」」」」」 ● 福司酒造 製造部(公式)Twitter: @fukutsukasa_ ● 醸し屋のInstagram : @fukutsukasa.kazuma ■五色彩雲ブランドページ URL:https://goshiki-no-kumo.com/ ■五色彩雲Noteページ URL:https://note.com/goshiki_no_kumo  ■ 採用情報はコチラから 五色彩雲シリーズのお取り扱い店舗はコチラからどうぞ。 |
| 2026.02.16 |
山と山のあいだで考えること


今の蔵の様子はというと、山と山の間。
谷というほど落ち着いているわけではありませんが、 大吟醸の仕込みを終え、搾りまでの“見守る期間”に入っています。 もうどうすることもできない段階。 あとは信じて待つだけです。 好調かと聞かれれば、 「好調と信じたい」が本音。 毎年そうですが、「今年は完璧だ」 なんて思えたことはありません。 いつも不安との戦いです。 この“動かせない時間”の間に、 3月までにまとめなければならない資料を整理しながら、 五色彩雲やその他の企画をじわじわと考えています。 原料価格の高騰を受けて、 どう価値を載せるのか。 どこまで価格転嫁できるのか。 正直、ここも自信はありません。 うまい酒を造ることは前提。 その上で「価格が上がる理由」をどう提示できるか。 今回の原料米高騰は、 ある意味、強制的にレベルを上げさせられているようなものです。 若手の夜明けで出会った他の蔵も、 きっと同じように自分自身と戦っているはず。 先日、とある蔵が 「すべてをオープンにするのは、 出し抜くためではなく、互いに切磋琢磨するため」 と発信していました。 私たちはまだ教える側ではなく、追いかける側。 そこまでの境地にはいません。 でも、前に立ったからこそ見える景色なのだろうとも思います。 福司はもともと地域の地酒。 けれど今は、地域外から来てくださる方や、 外で飲んでくださる方にも支えられ始めています。 そうなれば、基準値も変わる。 外の酒と比較される。 その上で、 「やっぱり地元の酒がうまい」 と思ってもらえる酒を造らなければならない。 五色彩雲は、そのための装置でもあります。 単に売るためのブランドではなく、 外とつながり、手法や考え方を吸収し、 福司の酒質そのものを引き上げる役割。 福司が担う酒、 五色彩雲が担う酒。 どちらもあっていい。 福司らしさを磨きながら、 五色彩雲で挑戦し、 その経験をまた福司に還元する。 そういう循環を作れたら理想です。 ということで、 どうしたら他の蔵に負けない酒になるのか。 今年の五色彩雲にも、工夫を入れたい。 うううううぅぅぅぅぅ…… また産みの苦しみが始まります(笑)。 うううううぅぅぅぅ。 美味くしたい。  本日もAI画伯に挿絵を提供していただいたのですが なんか変だけど仕方ないですね(笑) 」」」」」」」」」」」」」 SNS情報 」」」」」」」」」」」」」」 ● 福司酒造 製造部(公式)Twitter: @fukutsukasa_ ● 醸し屋のInstagram : @fukutsukasa.kazuma ■五色彩雲ブランドページ URL:https://goshiki-no-kumo.com/ ■五色彩雲Noteページ URL:https://note.com/goshiki_no_kumo  ■ 採用情報はコチラから 五色彩雲シリーズのお取り扱い店舗はコチラからどうぞ。 |
| 2026.02.13 |
写真と、酒と、プロの仕事


昨日のブログに書きました、「海と酒」のイベントの写真を
春日井製菓様から共有していただきました。 すごいいい写真ばかりで、素敵なイベントだったんだな~という感想 私自分のトークの部分しか参加していなかったので 全体の雰囲気まではわからないんですよね。    こういう写真が撮れるってことは釧路はいい街なんだろうなと。 素敵な写真を見ると、その一日が特別な時間のように感じられますよね。 でも実際は、日常の中にある風景だったりします。 私たちは当たり前に見過ごしているものを、 写真という形で「時間と空間を切り取る」ことで、特別に見せている。 写真が上手な人というのは、 この“日常のあたりまえ”を特別に変えられる人なのだろうと思います。 いつも見慣れている景色ですら、違って見える。 あれは本当にすごい。 蔵の仕事も、私たちにとっては日常です。 でも、プロのカメラマンにお願いすれば、 きっとまったく違う世界に見えるのでしょう。 素人が撮れば「作業場」。 でも見せ方一つで、神秘的にもなり、 息遣いや温度、音まで伝わってきそうになる。 誰でも簡単に撮れるなら、プロという仕事は存在しません。 でも、写真の上手な人が街に増えたら、 その街はもっと魅力的になるのかもしれません。 五色彩雲は、福司の中では少し特別な存在です。 ここまでプロの力を積極的に取り入れた商品は、 これまでの福司にはなかったかもしれません。 昔は、棚に並んだ酒の中から選ばれる時代でした。 町の商店で、顔なじみの人から買う。 「いつものやつでいいよ」という買い方。 私も子どもの頃、祖母に頼まれて豆腐屋さんに買いに行っていました。 そういう時代を、ぎりぎり知っています。 でも今は違います。 楽天やAmazon、地方の酒屋さんから取り寄せる時代。 棚の中で比較されるのではなく、 画面越しで「どんな酒なんだ?」と問われる。 味だけではなく、 背景や思想、ストーリーまでが選ばれる理由になります。 それがなければ、情報は一気に薄くなる。 似たような説明文の中では、印象に残らない。 その時代の中で、福司の商品をどう選んでもらうか。 五色彩雲は、そうした問いを試験的に探るレーベルでもあります。 札幌や東京の酒屋さんに扱っていただく中で、 全国の蔵が何をしているのか、 自分たちに何が足りないのか、 何が強みになり得るのか。 外に出て初めて見えたことも多くあります。 選ばれる理由を私たちが用意しても、 それが伝わらなければ、価値にはなりません。 同じ風景を切り取っても、 プロと素人では伝わり方がまったく違う。 手作りも大事。 でも、やはりプロの力は大きい。 もちろん、お願いすればお金はかかります。 けれどその経験値は、地域の中に残る。 互いにプロのレベルを高め合えば、 街そのものの魅力も上がるはず。 まだ、この地域はもっとレベルを上げられる。 そう気が付かされたイベントでもありました。 」」」」」」」」」」」」」 SNS情報 」」」」」」」」」」」」」」 ● 福司酒造 製造部(公式)Twitter: @fukutsukasa_ ● 醸し屋のInstagram : @fukutsukasa.kazuma ■五色彩雲ブランドページ URL:https://goshiki-no-kumo.com/ ■五色彩雲Noteページ URL:https://note.com/goshiki_no_kumo  ■ 採用情報はコチラから 五色彩雲シリーズのお取り扱い店舗はコチラからどうぞ。 |
| 2026.02.12 |
酒蔵が“話す”意味


昨日、釧路市で行われた春日井製菓様主催の「海と酒」というイベントで、
お酒部門のトークに登壇させていただきました。 この時期にこうした登壇をお受けすることは、ほとんどありません。 今回は少し特別でした。 主催に関わっていた清水さんは、かつて私が青年団体で例会を行った際、 こちらのお願いで登壇してくださった方。 そのご縁と御恩があり、今回は私が引き受ける番だと感じ、 参加させていただきました。 会場では、久しぶりに地域の皆さんと顔を合わせることができましたし、 同じ地域で異なる酒を造る醸造家の皆さんとも新たな接点ができました。 将来的に技術や情報を共有できる関係になれば それもまた地域の力になるはずです。 また、日頃からお世話になっている地元スーパー「雷さとう」の社長様とも 意見交換をさせていただき、 「地域をどう盛り上げていくか」という話ができたのも、 大きな収穫でした。 会場には福司だけでなく、 五色彩雲の試飲スペースも用意していただきました。 地域の方に直接味わっていただけたことは、 参加して良かったと素直に思える瞬間でした。 もっと酒の話をしたいくらいでしたが、時間の都合で断念。 いつもは文章で発信していますが、 やはり“声で届ける”ことの力は大きいと感じました。 表情や間、言葉の温度。 それらは文章とはまた違う形で伝わります。 以前、とある酒屋さんに言われたことがあります。 「これまでは酒蔵は酒屋に販売を任せていれば成り立っていた。 でも今は違う。酒屋さんもお客様が減る時代。 蔵自身が消費者とつながろうとしないと、商品は動かない」 その言葉は、ずっと心に残っています。 昨年「若手の夜明け」に出させていただいたときも、 知名度の重要性を実感しました。 限られたチケットの中で、どの蔵に使うか。 やはり“知っている蔵”が選ばれやすい。 イベントに出ることがゴールではなく、 そこから何を持ち帰れるか。 そのためには、普段から蔵の存在を知ってもらう 努力が必要なのだと気づきました。 発信は、売るためだけのものではありません。 “思い出してもらうため”の行為でもあります。 最近は動画での発信に力を入れる蔵も増えてきました。 私自身も、音声やポッドキャストのような形で届けられないかと考えています。 動画よりハードルが低く、寝転びながらでも収録できるかもしれませんし(笑)。 というのは冗談ですが、ちょっと本気で考えています。 五色彩雲でも、少しだけ動画投稿を始めています。 Instagramにアップしていますので、よければ覗いてみてください。 こちらに試験的に埋め込んでみましたが・・・・見れるかな? 」」」」」」」」」」」」」 SNS情報 」」」」」」」」」」」」」」 ● 福司酒造 製造部(公式)Twitter: @fukutsukasa_ ● 醸し屋のInstagram : @fukutsukasa.kazuma ■五色彩雲ブランドページ URL:https://goshiki-no-kumo.com/ ■五色彩雲Noteページ URL:https://note.com/goshiki_no_kumo  ■ 採用情報はコチラから 五色彩雲シリーズのお取り扱い店舗はコチラからどうぞ。 |
| 2026.02.10 |
北海道に来たら、これ飲んでねって載りました


ここ数日の天候不順で、青森あたりを中心に貨物が止まっている
という噂を耳にしていました。(釧路は天気いいんですけどね) その影響なのか、先週5日発売予定だった毎年2月号の『日本酒 dancyu』が、 ようやく昨日、釧路でも店頭に並んだようです。 昨日、本屋が帰り道だった蔵人から 「売ってましたよ、dancyu」と教えてもらいました。 チーム福司では、この数日ほぼ毎日のように、 本屋を入れ替わりでチェックしていました(笑) まぁ結果的にですが。 発売されていないのに「読んでください」と言うわけにもいかず、 この日を静かに待っていたところです。 今回発売されたdancyuには、福司のブランドから商品が掲載されています。 「この都道府県に行ったら飲みたい酒」という企画。 内容については、ぜひ実際に本を手に取って読んでいただければと思います。  昨年度は五色彩雲、 今年は福司。 双方のブランドを掲載していただけたのは、 率直にうれしい出来事です。 ただ、醸し屋としての目標は「載ること」ではありません。 蔵そのものを取材してもらえるだけの中身を、きちんと育てること。 そういう意味では、今回の掲載もまだ入り口だと感じています。 20年ほど前、社長と 「いつかdancyuに載せてもらえるようになれたらいいですね」 と話していたことがあります。 次は、もっと深く知ってもらえる形で取り上げてもらえるよう、 また一つずつ積み重ねていきたいです。 そんなdancyuの新刊を、 まだちゃんと読めてはいないのですが(笑)、 パラパラと眺めていて一つ感じたことがあります。 それは、アル添に対する視点が変わりつつある??ように見えたこと。 表現が正しいかは分かりませんが、 かつての強い純米主義に対して、 「一度立ち止まって見直してみませんか?」 と、メディア側から問いかけているようにも感じました。 SNSでも、アル添について丁寧に説明する蔵が少しずつ増えています。 一時期は、「アル添」という言葉を出しただけで叩かれるような空気もありました。 造り手からすると、「辛口ください!」の一択と、 「純米じゃないとダメ」という考え方は、 そこまで大きく違わないようにも感じます。 どちらかを否定する必要はなく、 それぞれの良さがあって、好みを選べばいい。 それだけの話だと思っています。 福司でも、純米主義が強かった時代に、 アル添酒の製造量を減らすべきかどうか、という議論がありました。 たしか10年ほど前の話です。 そのときに行き着いたのは、 福司の根っこは「地酒」であり、 アル添酒に支えられてきた歴史がある、という事実でした。 アル添を否定することは、 自分たちが歩んできた歴史を否定することになる。 そして、それを飲み続けて支えてくださった方々に対して、失礼ではないか。 そんな結論でした。 (社長は、もともとそう考えていたと思います) アル添には、アル添のうまさがあります。 そして、アル添は決して簡単な技術ではありません。 以前、東京のお酒屋さんに福司の普通酒を飲んでいただいたとき、 「こんな普通酒を、今の時代にまだ造っている蔵があるんですね」 と言われたことがあります。 (それまで当たり前に作っていたので気が付いてなかった) そもそも普通酒を造っている蔵自体が減っていますし、 力を入れている蔵も多くはありません。 ですが、福司では普通酒も決して手を抜いていません。 この地域では、今でも普通酒の消費が多い。 メインではないにせよ、 「適当に造っていい酒」ではないのです。 本気で造る普通酒は、実はとても難しい分野だと思っています。 日本酒の区分の中で、最も自由度が高いのが普通酒。 裏を返せば、可能性と余白が一番多い酒でもある。 大吟醸よりも、 醸し屋としては、よほど面白いことができる余地がある。 地味ですが、そんなふうに注目しています。 気になった方は是非福司を飲んでみて! dancyuも読んでください。 」」」」」」」」」」」」」 SNS情報 」」」」」」」」」」」」」」 ● 福司酒造 製造部(公式)Twitter: @fukutsukasa_ ● 醸し屋のInstagram : @fukutsukasa.kazuma ■五色彩雲ブランドページ URL:https://goshiki-no-kumo.com/ ■五色彩雲Noteページ URL:https://note.com/goshiki_no_kumo  ■ 採用情報はコチラから 五色彩雲シリーズのお取り扱い店舗はコチラからどうぞ。 |